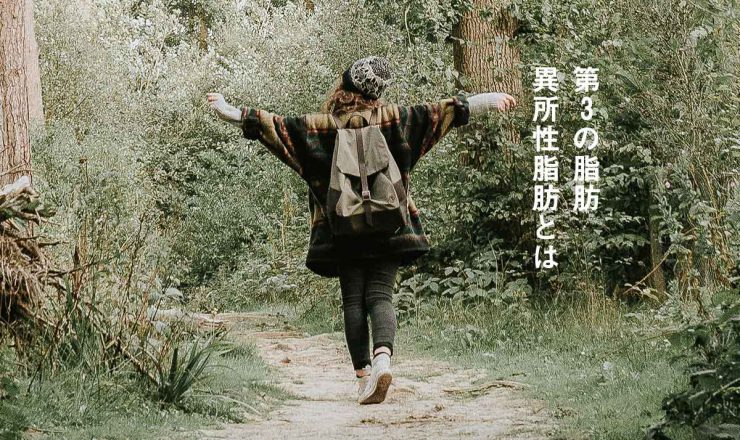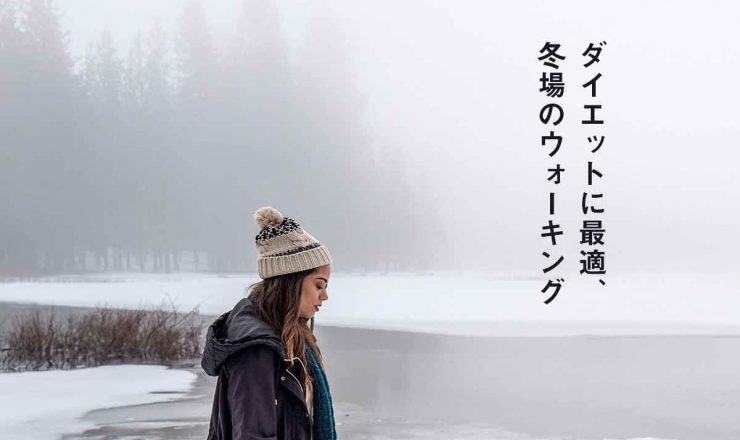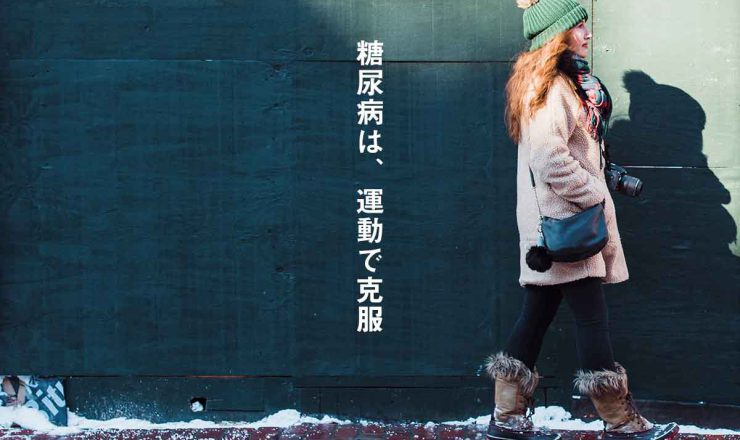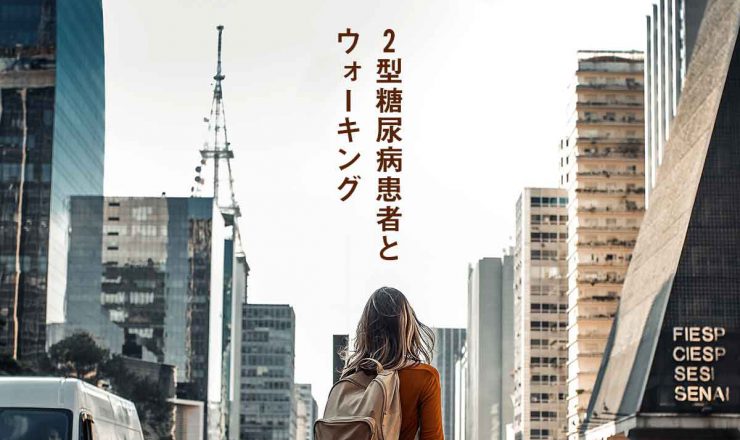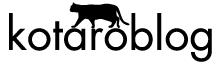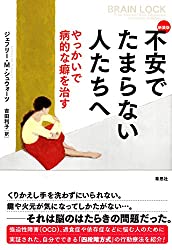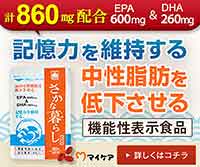部署が変わって3ヶ月、最近めまいや吐きがして、朝、会社の前まで来ると、足がガタガタ震える、、、不安でたまらない
と、いう方へ。

適応障害の典型的な症状ですね。
あまり無理しないで、休養も大切です。
何よりも、障害になっているものを
特定して、楽になってください。
今回は、適応障害の話です。
■もくじ
- めまいや吐き気などがおこる【適応障害】とは
- ストレスの原因を取り除けば楽になる適応障害の治療法
この記事を書いている僕(コータロー)は、健康食品を販売して15年ほど。
めまいや吐き気などがおこる【適応障害】とは

5年後には4割がうつ病になる適応障害とは
適応障害は、特定可能な、ある状況や出来事(ストレス因)によって引き起こされ、その人にとっては大変つらく、めまいがしたり、頭痛がしたりと日常生活にも支障をきたすもので、ストレス因の始まりから3ヶ月以内に症状が現れるものです。
たとえば、、、
- 会社内で移動人事があり、違う部署にいったところ、上司との反りが合わない
- 会社に入社したけれど、同僚とうまく行かず孤立している
- 結婚したけれど、夫の両親とうまく付き合えない
など、場所や人間関係、または、経済事情等のあらゆる場合があります。
適応障害のストレス因は、多種多様
ストレス因は、種々様々です。
- 失業
- 失恋
- 人事移動
- 人間関係
- 金銭問題
- 恋愛の挫折
- 家族の問題
- 同僚の問題
- 兄弟の問題
- 地域社会問題 など
PTSD(心的外傷後ストレス障害)にみられるような、明確な外傷的できごとである必要はありません。
また、ほかの病気があるために適応障害ではないと判断される場合があります。
たとえば、、、
統合失調症やうつ病などの気分障害や不安障害などがみられれば、こちらの疾病が優先されます
また、、、
適応障害と診断されても、40%の人が、5年後にはうつ病になっています
これは、、、
適応障害は、その後の重篤な病気の前段階の可能性があります
適応障害の症状とは
適応障害は、特定可能なストレス因によって生じますが、そのストレス因が消失した後の6ヶ月を超えて続くことはなく、以下のような症状があります。その症状は、複数を兼ねることもあります。
- 抑うつ気分
- 不安
- 違法行為
たとえば、、、
情緒面では、抑うつ気分、不安、怒り、焦り
行動面では、行きすぎた飲酒や暴食、無断欠席、無謀な運転やけんかなどの攻撃的な行動
不安が強く緊張が高まると、体の症状としてどきどきしたり、汗をかいたり、めまいなどがみられます。

適応障害は、ストレス因を離れると改善することが多い
ある状況や出来事(ストレス因)によって引き起こされる適応障害ですが、このストレス因を離れると改善することが多いです。
たとえば、、、
そのストレス因が、会社内の問題だとすると、勤務中は憂うつで不安が多く、緊張して手が震えたり、めまいがしたり、汗をかいたりしますが、仕事のない休日には、憂うつな気分は少し楽になり、趣味を楽しむことができる場合があります
うつ病と適応障害の違いは、うつ病の場合は、休日になっても憂うつが取れません。
ですから、、、
持続的な憂うつ気分、趣味・関心の喪失や食欲の低下、あるいは、不眠などが長く2週間以上続く場合は、うつ病と診断される可能性が高くなります。
ストレスの原因を取り除けば楽になる適応障害の治療法
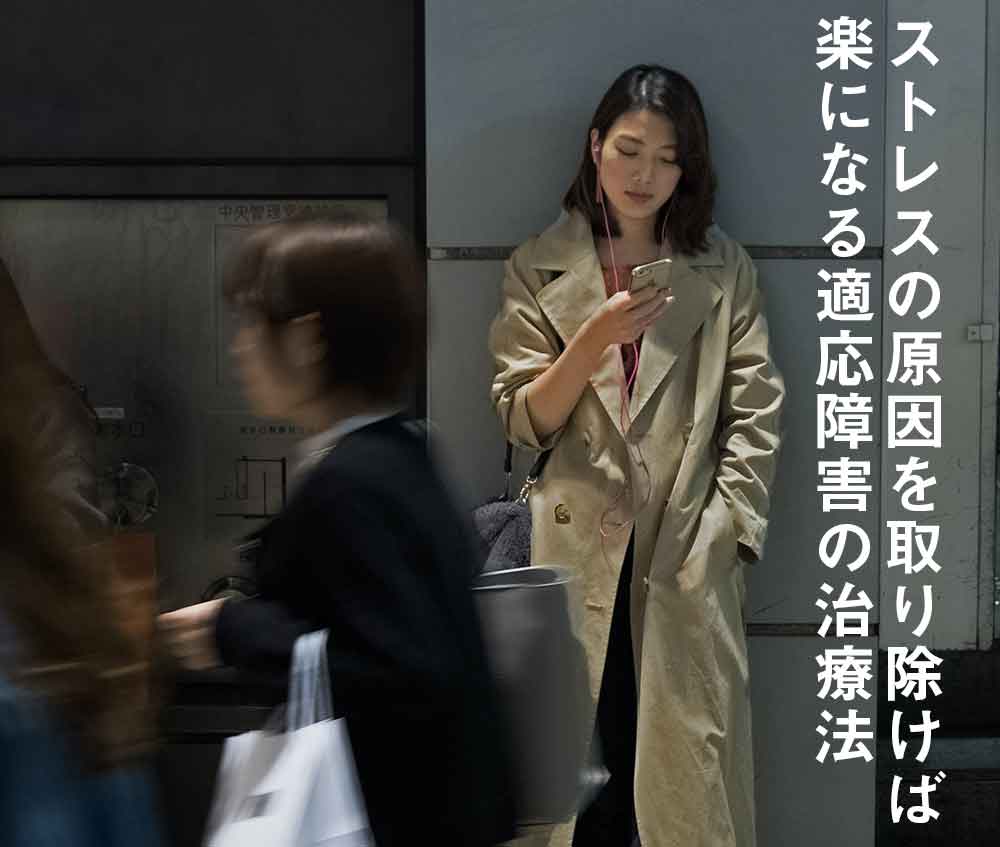
適応障害の治療法は、3種類
適応障害の治療の1つは、「ストレス因の除去」です。そして、ストレス耐性を高めること、人によってはストレスでもストレスにならない人もいるので、耐性を高めること。また、症状に対してのカウンセリングです。
| 適応障害の治療法は、3種類 | |
| ストレス因の除去 | ストレス因の除去とは、環境調整することです。たとえば暴力をふるう恋人から離れるために、ほかの人に助けを求めるなどがこれにあたるでしょう。 ストレス因が取り除ける、あるいは回避できるものであればいいのですが、家族のように動かせないもの、離れるのが難しいものもあります。こうなるとストレス因の除去だけではうまくいきませんので、次のステップも必要となります。 |
| 本人の適応力を高める | ストレス因に対して本人はどのように受け止めているかを考えていくと、その人の受け止め方にパターンがあることが多くみられます。 このパターンに対してアプローチしていくのが認知行動療法と呼ばれるカウンセリング方法です。また現在抱えている問題と症状自体に焦点を当てて協同的に解決方法を見出していく問題解決療法もあります。 この認知行動療法も問題解決療法も、治療者と治療を受ける人が協同して行っていくものですが、基本的には治療を受ける人自身が主体的に取り組むことが大切です。 |
| 情緒面や行動面への介入 | 情緒面や行動面での症状に対しては、薬物療法という方法もあります。
不安や不眠などに対してはベンゾジアゼピン系の薬、うつ状態に対して抗うつ薬を使うこともあります。 ただし適応障害の薬物療法は「症状に対して薬を使う」という対症療法になります。根本的な治療ではありません。 つまり適応障害の治療は薬物療法だけではうまくいかないことが多いため、環境調整やカウンセリングが重要になっています。 |
厚生労働省:みんなのメンタルヘルス:適応障害
適応障害の症例を紹介
適応障害の症例を知ることで、どのような状況が適応障害なのかが把握できます。
異動後、起きられずに吐き気も
営業職Cさん(29歳、男性)の場合
大学院修了後に研究職として入社しました。これまで、専攻内容に合った研究だったので仕事も楽しくできていました。ところが、最近の不況で、研究部門の閉鎖が決まり、3カ月前に技術営業に異動になってからは、仕事がつらくてたまりません。営業部長が猛烈サラリーマンタイプで、何かと怒鳴られてしまいます。
それから、会社に出勤しなければいけないと思うと憂うつで、朝起きるのがどんどん苦痛になり、吐き気を感じることも多くなりました。とうとう会社の前まで行っても、足が動かず冷や汗が出てきて、社内に入ることができなくなってしまい、近くの病院に行くことにしたのです。
心療内科では「適応障害」と診断され、通院治療することになりました。その後、人事部とも相談し、職種に無理があるということから、品質管理部門に異動になり、苦手な営業部長とうまくやらなくてはいけないというストレスはなくなりました。つらかった症状も比較的早くなくなり、かなり楽になりました。また、通院の際には、カウンセラーから心理療法を受け、自分の考え方を少しずつ修正できるようになっています。
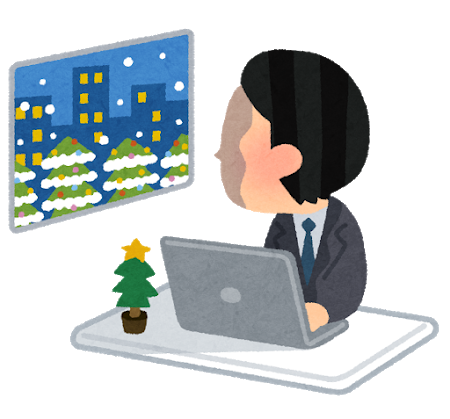
ストレス因は、父親だった
LaLa 21歳 女性 アルバイト 未婚
適応障害―原因がわからない
適応障害と診断を受け大学を休学していますが、現在、復学に向けてアルバイトをしています。中学1年の頃から軽い頭痛はあったのですが、2年生の春から学校に行こうとすると頭痛がひどくなり、登校できなくなってしまいました。
原因が分からず、この時初めて精神科に行き、”適応障害”と診断されました。ストレスが原因だと言われ、カウンセリングも受けました。学校に行こうとすると頭痛がひどくなるので、学校に原因があるのではとのことでしたが、友達は多いほうではありませんが仲の良い友達もいるし、いじめをうけたこともなく、学校も嫌いではありませんでした。それでも、中学2年生の時は頭痛もひどくなり登校できず、辛くて辛くてしょうがなかったので、一日中ベッドの中にいました。
頭が痛いので寝られなくて食欲もなく、身体もだるくて何も手がつけられない状態でした。ところがあれほど辛かった頭痛が、中学3年生になる年に軽くなったのです。精神科でいただいていた薬が効いたのだろうと思い、そのおかげでかろうじて中学も卒業でき、高校にも進学できました。しかし、再び頭痛がひどくなり、高校2年の夏に退学。その後、また不思議と調子の良い時もあったので、大学受験をするために高等学校卒業程度認定試験を受け、大学にも合格しました。晴れて大学1年生となりサークルにも入り、アルバイトもできるようになったのです。しかし、再び休学することになってしまいました。
この時は、頭痛だけではなくうつ病にも近かったと思います。
適応障害―原因がわかった
大学を休学したばかりの頃辛かったのは、周りの人に大変さを理解してもらえなかったことです。特に父からは、なまけているとか、たいしたことないとか、母が甘やかしているからとかよく言われました。あまりにもひどい頭痛だったので、大学病院で調べてもらったり、セカンドオピニオンとして他の精神科医のところへも行ったりしてみました。いわゆるドクターショッピングです。なかなか原因が分からず、1年経った頃、精神科の先生やカウンセラーとの話から原因が少しずつ分かっていきました。
ストレス、頭痛の原因は、私自身、何ごとにも我慢してしまう性格もあるのですが、もうひとつは父の影響でした。原因がわかった時はとても驚きましたが、思い当たることも多々ありました。中学2年生の時に頭痛がひどくなったのは、父が仕事で抱えていたストレスを私がもろに受けてしまっていたとか、中学3年生の時に頭痛が治まったのは、父が転勤になり単身赴任をしていたから影響を受けずにすんだからではないだろうかとか、それほど父の影響が強かったみたいです。
思い返せば、父の性格は起伏が激しく、私はどちらかというとおとなしいほうだったので、そのまま受け入れてしまい、自分では気がつかない中でダメージを受けてしまっていたようです。もちろん母は驚いていました。自分の性格や父の影響が、ストレスの原因であり頭痛の種であったということは分かりましたが、どのように対処すればよいか分からず、しばらく一進一退の日々でした。
適応障害―症状が軽減
調子の良い時は買い物に出かけたりもしていましたが、コーヒーを飲みたくてカフェに入っても鳴っている音楽に反応して頭痛が起こったり、車や電車の音も辛く、家にこもる日もありました。パソコンも画面の光が強すぎて、インターネットで何かを見るとか調べるとか、メールで友達とやりとりするのが大変な時もありました。少しでも気持ちを軽くしようとアロマテラピーやヨガも自宅でやってみました。いろいろ試しているうちに、薬も自分にあっていることで落ち着いてきました。
父は転勤から戻っていますが、仕事が忙しく顔をあわすことがないので影響を受けることもなく、気持ちが少し晴れる日が増えてきました。調子のよい時とよくない時の繰り返しはありますが、それでも少しずつ良くなっていることがわかるくらい、母からも顔が明るくなったと言われます。
少しずつですが食欲も出始め、食欲が出ると体力もついてくるので、そろそろ大学に復学したいと思い、今、アルバイトには週2日~3日、4時間入っています。頭痛はまったくなくなったわけではないので、朝、起きられなくて辛い日もありますが、なんとか頭痛とはつきあいながら過ごしていこうと思っています。うれしいことに薬も少し弱い薬に変わりました。子どもの頃なかなか自分のことをうまく話ができずにいたのと同じように、今でも自分のことを話すのは苦手です。それでもあまり悩まないように、我慢しないようにしています。
今後は、父の影響を受けても大丈夫なように対処を考えていきたいと思っています。

上司からの叱責がもととなり適応障害に
上司からの叱責がもととなり、身体症状を伴った適応障害を引き起こした
約1年前より、現在のIT関連の会社に勤めていましたが、約3か月前に、仕事上のことで、上司に叱責されたことをきっかけにめまい、吐き気などの身体症状が出現しました。
7月に精神科を受診。受診時は、やや抑うつ気味で、仕事の上での自信を喪失しているように思われました。治療は、自律訓練法(筋弛緩による不安軽減法)を教示し、不安時にロラゼパム0.5mgの頓用から開始しました。1週間後に通院し、ロラゼパムを一日3回ほど服用したとのことでした。系統的脱感作法(自律訓練法を用いたイメージ療法)を行うために、不安階層表(一番ストレスのかかる場面を100点として10点刻み毎に不安の低い場面の順に並べた表)を作成させ、30点くらいの不安場面を自律訓練中にイメージすることから開始しました。その後、2週間毎に通院しましたが、上司が目の前に現れると心拍数が早くなり体の震えを感じることは、まだ持続しているものの、徐々に自覚症状としては軽快してきました。
しかし、受診開始から3か月後には、吐き気などの体調不良で会社を休むようになりました。内科で精査をするも、問題ないとのことでした。この頃より、抑うつ気分が強くなったために、塩酸セルトラリンを追加し、抑うつ症状の改善をはかるとともに、職場内での本人の孤立化を防ぐために、直属以外の他の部門の上司とも仕事のことを相談するように働きかけました。また、抑うつ気分については、診断書を作成し、職場内のストレス環境の可能性を指摘し、本人の能力を生かせるための配置転換も含めた職場内での配慮を依頼しました。その結果、受診開始から約1年後に部署変更があり、直属の上司が変わり、抑うつ気分も改善傾向となりました。
その後、現在の上司とは、比較的、仕事上でのトラブルもなく、うまくやれています。しかし、会社内で以前の上司と会ったときは、今でも、体の震えを感じたりすることがあるとのことです。

以上。
また、次回。