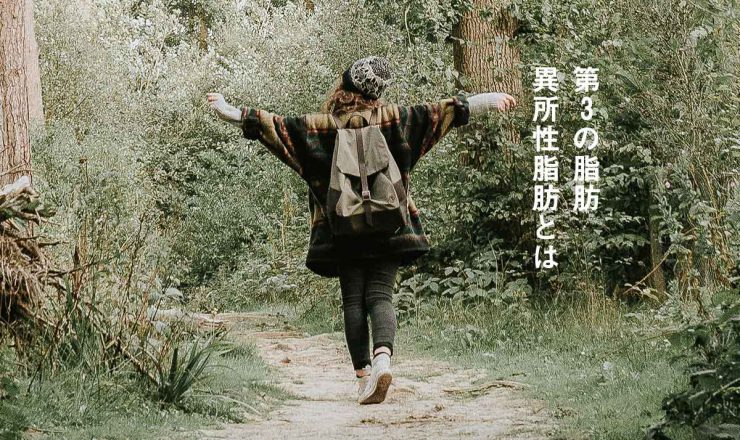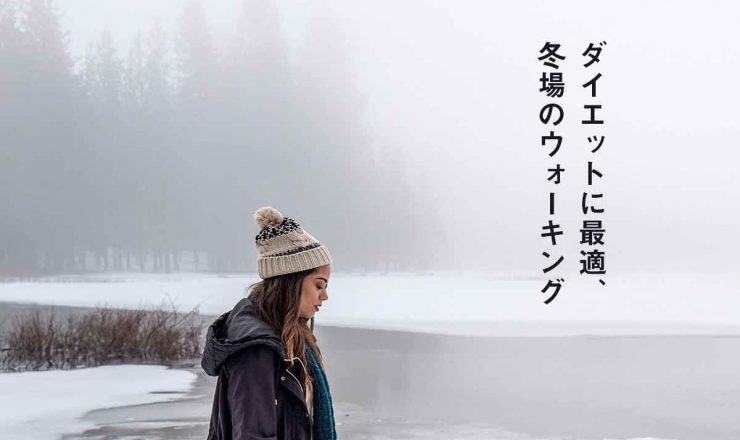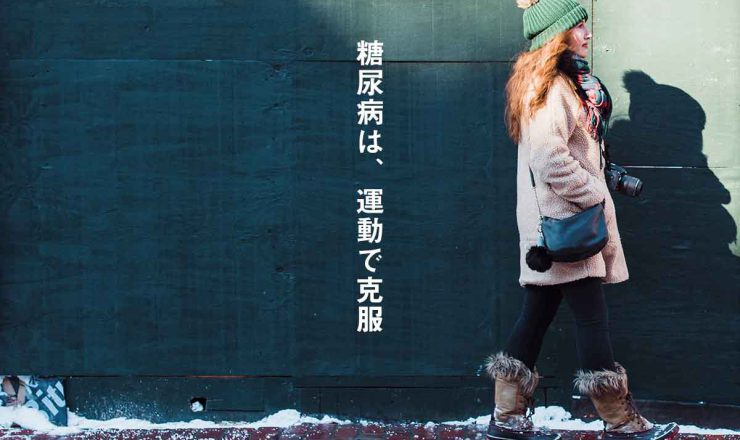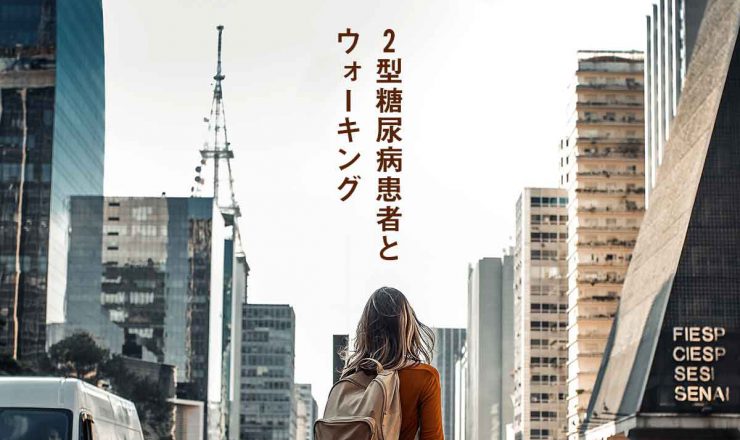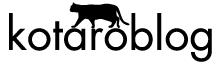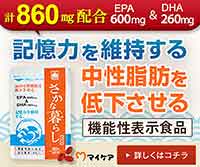私すぐ緊張するタイプ。ドキドキして下痢になったり、ガスがたまってしまい多くの人がいるところが苦手・・・ちょっと引きこもりがち。
と、いう方へ

ストレスや緊張を抱えると
下痢になったり、
逆に便秘になったりします。
それは、過敏性腸症候群ですね。
今回は、過敏性腸症候群の話です。
詳しく、解説します。
■もくじ
- ストレスを抱える現代女性の多い過敏性腸症候群
- 過敏性腸症候群(IBS)には、どうして起こるのか
- 過敏性腸症候群は、生活習慣を見直すことで改善できる
この記事を書いている僕(コータロー)は、健康食品を販売して15年ほど。
ストレスを抱える現代女性に多い過敏性腸症候群

先進国では、人口の約1割強が過敏性腸症候群
不快感や痛みなどの自覚症状があっても炎症が見つからない現代病ともいわれる、疾病を取り上げています。
- 非びらん性胃食道逆流症(Non-Erosive Reflux Disease : NERD)
- 機能性ディスペプシア(Functional Dyspepsia : FD)
- 過敏性腸症候群(Irritable Bowel Syndrome : IBS)
逆流性食道炎は、新国民病とまでいわれています。30年で10倍にも増えていますし、【機能性ディスペプシア】は、胃もたれや胃痛があっても炎症が見つからない現代病です。
非びらん性胃食道逆流症(Non-Erosive Reflux Disease : NERD)

【就寝前4時間は食べてはいけない】のですが、ついつい食べてすぐ寝てしまう人が多いのです。このような乱れた生活習慣を続けていくと、逆流性食道炎から誤嚥性肺炎になってしまいます。誤嚥性肺炎は、逆流性食道炎の合併症です。
機能性ディスペプシア(Functional Dyspepsia : FD)

日本人の10人に1人は、この【機能性ディスペプシア】に罹患しているといわれています。胃に不快感があり病院に行って診察された人の割合では、4割ほどが機能性ディスペプシア(FD)が見つかるようです。
そして、今回取り上げるのは、過敏性腸症候群(Irritable Bowel Syndrome : IBS)
過敏性腸症候群(IBS)は、当然ですが大腸に炎症や腫瘍がないことが条件です。この【過敏性腸症候群】も検査をしても炎症や腫瘍などの異常が見つからないけど、下痢を起こしたり、便秘になったり、お腹が痛くなったりをくり返します。
過敏性腸症候群(IBS)の特徴は【比較的女性に多い】
慢性的な下痢、長引く便秘などをかかえて悩んでいる人はかなりの数に上っています。お腹にガスがたまったりして、人に相談しづらく悩みを抱えている人が多いです。
その特徴は、、、
- 先進国では、約1割強が過敏性腸症候群
- 消化器科を受診する患者の20~30%が、過敏性腸症候群
- 過敏性腸症候群は、比較的に女性に多い
- 年代的には女性では20才代と50才代、男性では30~40才代に多く見られる
- 受験などのストレスで、中高校生などの若年層にも過敏性腸症候群が発症している
過敏性腸症候群(IBS)の症状は
よくオナラがでたり、おなかがゴロゴロしたり、ゲップが出たりして、過敏性腸症候群になった人は人前に出たくないことが多いようです。
だいたいの症状を列記すると、、、
- 下痢または便秘が長く続いている
- 下痢と便秘を交互にくり返している
- 排便しても残便感がある
- ひんぱんに腹痛に襲われる
- 腹部に膨満感がある
- 腹部がゴロゴロなる
- 排便により腹痛や腹部の不快感が和らぐ
- よくオナラがでる
- よくゲップが出る
- 食欲が不振だ
- 吐き気やおう吐をする
などのたくさんの症状があります。
思春期に過敏性腸症候群になると不登校になる危険性も
思春期の神経が過敏な時期に、この過敏性腸症候群になってしまうと、お腹がゴロゴロ鳴ったりオナラがでたりするので、恥ずかしくなり不登校や引きこもりの原因になったりします。
過敏性腸症候群(IBS)には、4タイプにわけられる
この症状になる人はかなり多く、「今日は大切な会議がある」「みんなの前で発表しなければいけない」「今日から大学受験」など緊張したときに限って、下痢になったりします。
下痢型、便秘型、混合型、分類不能型の4タイプある
過敏性腸症候群には、便通の状態から分けて、4タイプにわけられ、そのタイプも男女に差がみられます。それは、腸の働きに性ホルモンが関係してるのではと考えられているようです。
| 下痢型: | 突如起こる下痢が特徴で、若い男性に多く、緊張してお腹をくだす。1日に何度もトイレにいく |
| 便秘型: | ストレスを感じると便秘が悪化。腸で便が停滞し、便意があってもコロコロとした固い便になる。年配女性に多い。排便するときにお腹が苦しくなることが多い |
| 混合型: | 下痢と便秘を交互に繰り返す。便の状態が変動する |
| 分類不能型: | ほかの3つのタイプのいずれにも属さないもの |
過敏性腸症候群を起こしている人は、胃の痛みや胃もたれ、胸やけを起こす人が多く、胃食道逆流症を合併することが多いようです。
過敏性腸症候群(IBS)には、国際基準がある
過敏性腸症候群(IBS)は、2006年に国際診断基準が改定されています。
| 最近3ヶ月間、月に4日以上腹痛が繰り返し起こり、次の項目の2つ以上があること | |
| 1 | 排便と症状が関連する |
| 2 | 排便頻度の変化を伴う |
| 3 | 便性状の変化を伴う |
| 期間としては6ヶ月以上前から症状があり、最近3ヶ月間は上記基準をみたすこと | |
→ 慶應大学:過敏性腸症候群(IBS)
過敏性腸症候群(IBS)は、どうして起こるのか
過敏性腸症候群(IBS)とストレスの関係
過敏性腸症候群(IBS)になってしまう原因の一番は、やっぱりストレスです。
過敏性腸症候群(IBS)を専門に研究している東北大学の福土審教授(行動医学)は、、、
IBSの人には、ストレスを抱えていても、性格的に感情を言葉に出来ない『失感情症』の人が多いのです。まず、自分のストレスを言葉にして、自覚することが大切です
→南東北新聞:第192号|過敏性腸症候群とは
と、語っています。

うつ状態の人も不眠症の人も過敏性腸症候群のリスクを抱えており、生活習慣の乱れで食事が不規則になった人もリスクがあります。
それは、、、
- 不規則だと腸の収縮リズムが崩れ、空腹時に腸が行う清掃機能がうまく働かなくなるからです
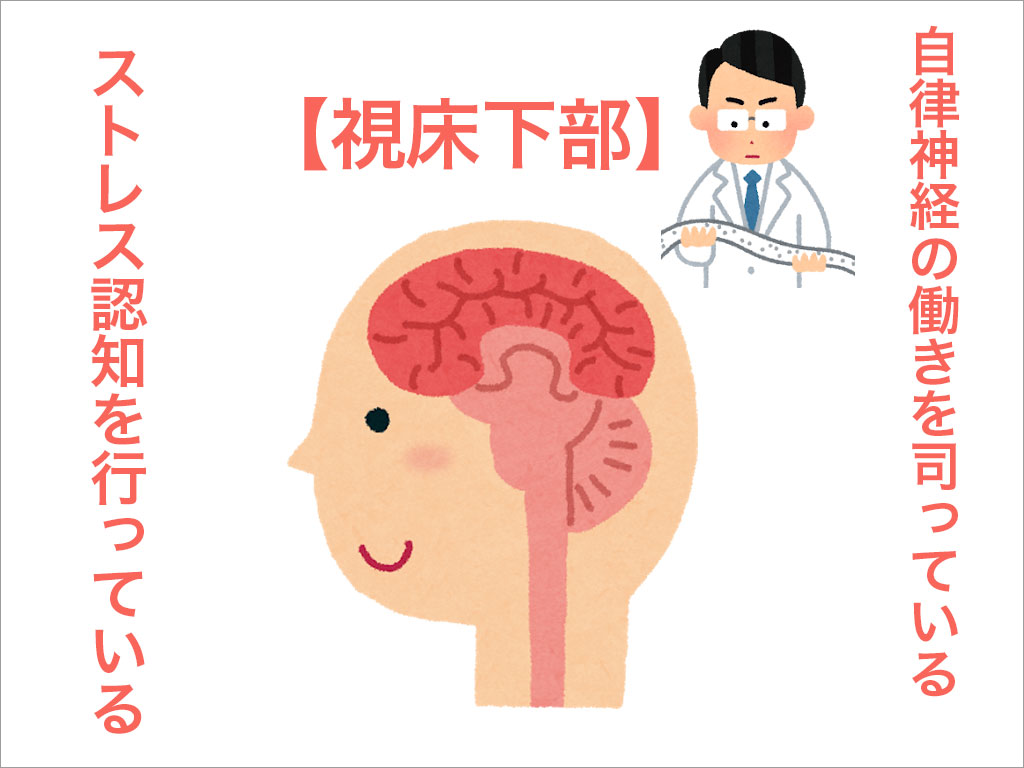
腸のリズムの崩れは、生活習慣の乱れ
私たちは、目や口を自分の意志で動かせますが、胃や腸は、自分の意志では動かせません。私たちの内臓の動きは自律神経が支配しています。
この自律神経は、脳の視床下部から出される命令によって動いています。ストレスが脳に入ってくると視床下部が反応して適切な司令を送れなくなってしまいます。
以前、この記事では、ストレスと摂食障害について説明しました。
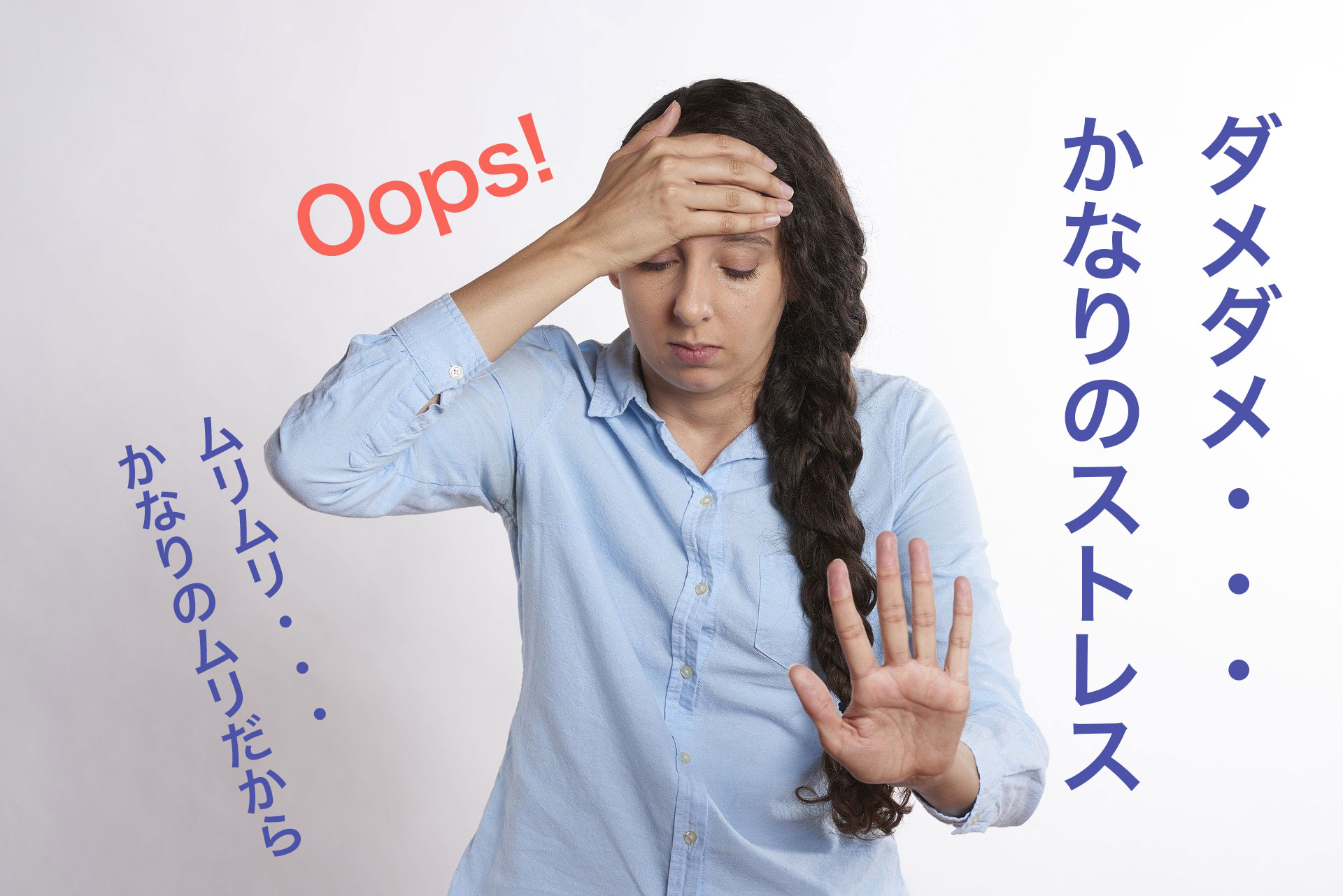
ストレス認知を行っているのも【視床下部】でしたが、自律神経の働きを司っているのも【視床下部】です。だから、ストレス状態が続くと自律神経のバランスが崩れるのはこのためです。
このストレスが原因で、人の身体のいろいろな場所で変調がおこります。たとえば、心臓、胃、腸など・・・
公的には、過敏性腸症候群(IBS)の原因はハッキリしないとなっていますが、ストレスとの関連性は非常に大きいといえます。
ですから、ストレスを解消することで過敏性腸症候群(IBS)を改善できます。
過敏性腸症候群は、生活習慣を見直すことで改善できる

スポーツなどで身体を動かし、ストレスを解消しよう
身体を動かすことは、[気晴らし]には最適なこと。また、軽いスポーツをすることで発汗すれば、血流もよくなります。
さらに、日光を浴びながら散歩をするのもよいでしょう。
ストレスをコントロールしよう
薬に頼るのは最終手段。薬によって緩和されるのは一時的なものと考えて、生活習慣を見直すことで改善できると思います。
- 軽いスポーツをしてみる
- 趣味を持ちストレスを発散させる
- 散歩をする
- 早起きをやってみる

など、昔からいわれているような活動的なことにチャレンジしてみるのが、過敏性腸症候群を改善する手段になると思います。
日々が、活動的な生活になれば睡眠の質が向上します
また、、、
食事も美味しくなります
過敏性腸症候群の注意点
最後に、過敏性腸症候群は、比較的誰でもなってしまうポピュラーな症状ですが、イカのような状態になったら黄色信号ですので、注意してください。
- 便に血が混じっている
- 貧血気味だ
- 熱があって体重が減ってきた
などの場合は、、、
- 潰瘍性大腸炎
- クローン病
- 大腸ガン
などの重大な病気の危険性があります。腹痛や便通の異常があまりにも長く続く場合は、消化器専門ドクターに診てもらうことが大切です。
以上。
また、次回。