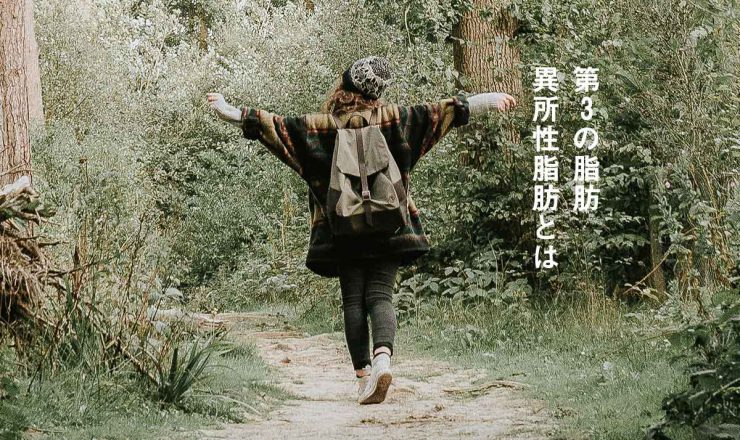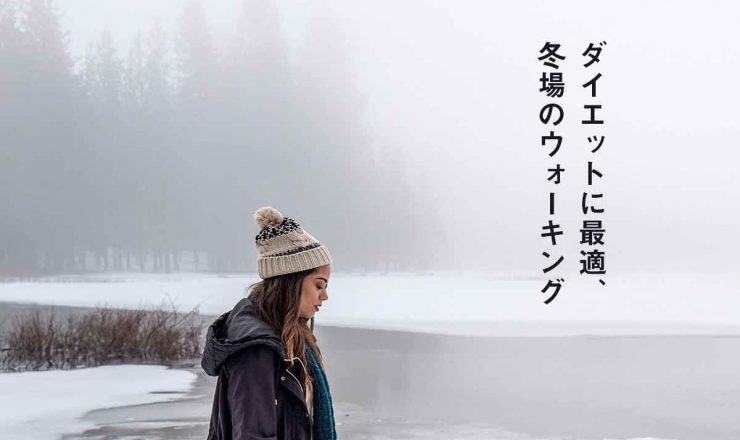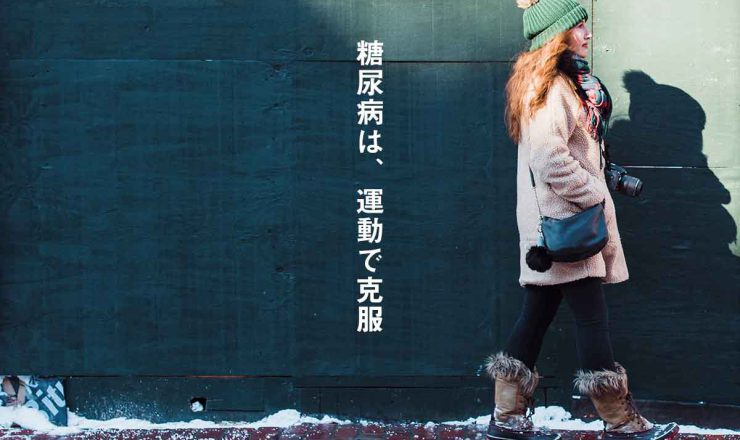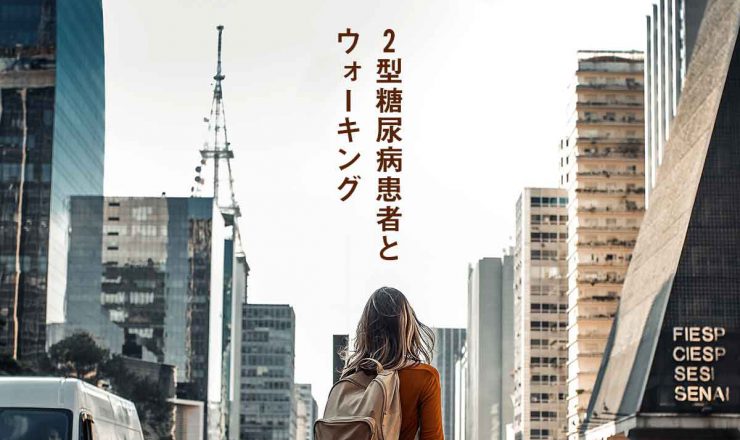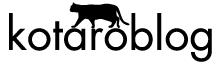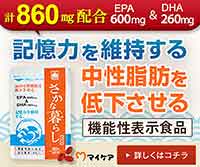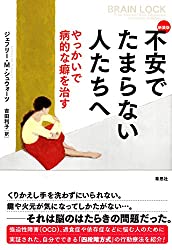疲れているのか、下車する駅が近づくと、電車内で突然不安が襲ってきます。どうしたらよいか不安で、もう通勤電車には乗りたくない。
と、いう方へ。
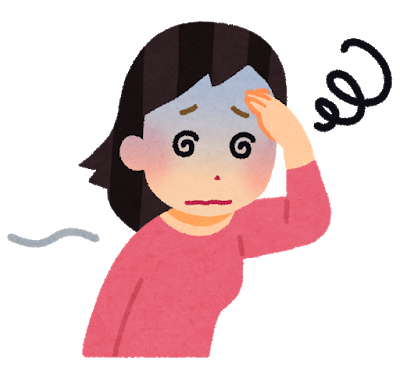
身体の調子は悪くないのに
突然襲ってくる恐怖感は、
パニック発作かもしれません。
今回は、パニック障害の話です。
■もくじ
- パニック障害とは
- パニック障害の治療とは
この記事を書いている僕(コータロー)は、健康食品を販売して15年ほど。
パニック障害とは
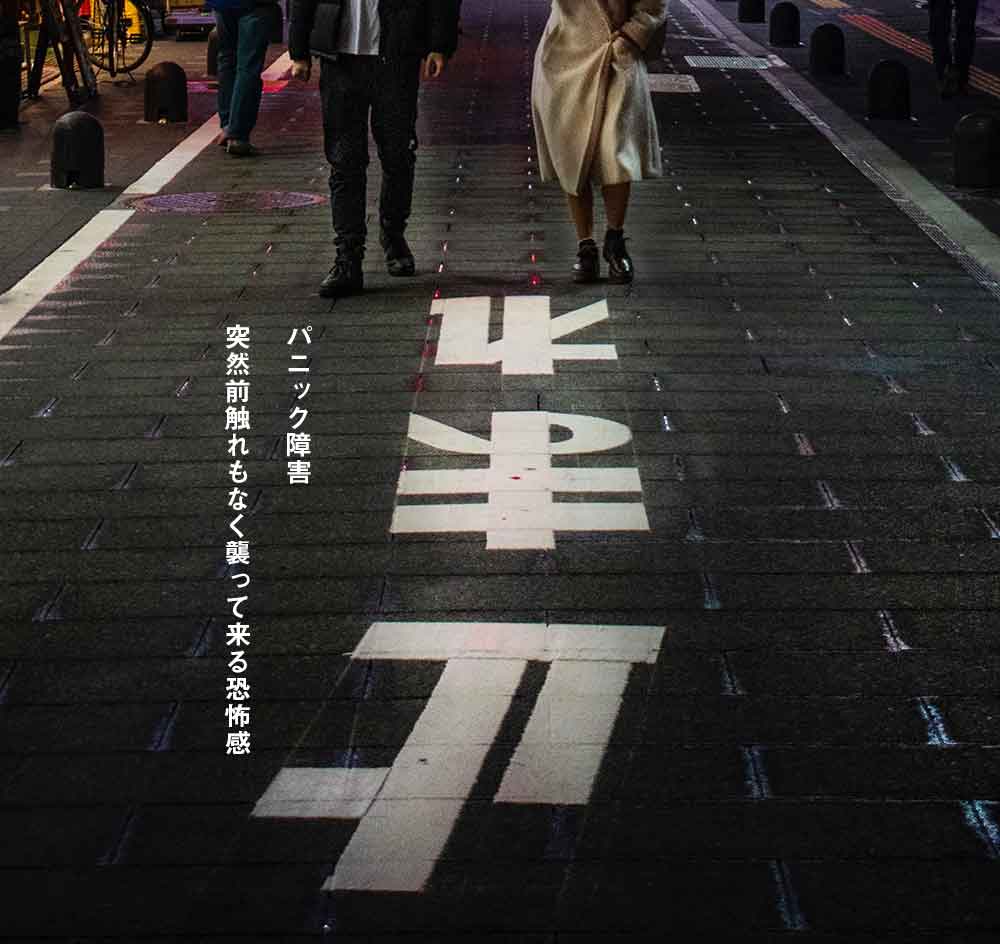
パニック障害の発作とは
パニック障害は、突然前触れもなく襲って来る恐怖感です。
パニック障害になると、死んでしまうのではと思うほどツラい症状があることも
身体の調子は悪くないのに強い不安感にともなって、、、
- 動悸
- 息苦しさ
- 呼吸困難
- 胸の痛み
- 苦悶感
- 吐き気
- お腹の違和感
- 汗
- めまい
- 寒気
などの症状がでます。身体に異変がでるので、「身体のどこかが悪いのか」と勘違いしがちです。そこで、内科や救急科に受信しても「何の異常もない」といわれることがよくあります。
しかし、パニック障害の発作は、耐えがたいほどツラいもの。
このままでは、、、
「このまま死んでしまうのでは・・・」「このまま発狂するかも」と思われるぐらいツラいものです
また、、、
パニック発作は、数分から数十分で治まります
さらに、、、
- 『この苦しい発作が過去2回以上起こり』
- 『あの苦しい発作が起きたらどうしよう・・』
- 『あの場所にいったら、また発作が起こるかも』
などと、心配になって、外出などが億劫になってしますのが、【パニック障害】です

パニック障害のおもな症状は
パニック障害は、2013年に『パニック症』と病名が変わりました。しかし、パニック障害という名称の方が、広く知られています。それは、有名スポーツ選手が自らを「パニック障害」だと公表したので認知されるようになりました。
※2013年に米国精神医学会からDSM-Ⅴが発表されました。
パニック障害の症状は、3つに分類される
そのパニック障害の症状は、3つに分類されます。
- パニック発作
- 予期不安
- 広場恐怖
パニック障害の症状:パニック発作
パニック発作は、強くて鋭い不安発作になります。この不安発作で交感神経が優位に働き、動悸や息苦しさ、呼吸困難や吐き気、汗や目眩を引きおこします。さらに、汗が噴き出し、寒さや暑さを感じます。
このパニック発作が何度もくり返されます
- 身体の症状
- 心臓がドキドキする、または心拍数が増加する
- 汗をかく
- 身震い、手足の震え
- 呼吸が早くなる、息苦しい
- 喉に何か詰まったような窒息感
- 胸の痛みまたは不快感
- 吐き気やおなかの不快感
- めまい、不安定感、頭が軽くなる、気が遠くなるような感じ
- 寒気またはほてり
- 身体のしびれ感、うずき感
- 今起こっていることが現実ではない感じ、自分が自分でない感じ
- 精神的な症状
- コントロール力を失う、気が狂ってしまいそうな恐怖
- このまま死んでしまうのではないかという恐怖
パニック障害の症状:予期不安
強くて鋭いパニック発作がくり返されると、、、
また起こるのではないかとさらに不安になります。これを、予期不安といいます
そして、この、、、
また起きるのではないかという不安は、発作そのものよりも「発作を起こした場所や状況」へと広がっていきます
パニック障害の症状:広場恐怖症
パニック障害の広場恐怖症とは、、、
以前発作がでた場所に行くと、あの強くて鋭い発作を思い出してしまい恐れてしまい、その場所や状況を避けることを指します
この、、、
広場恐怖症は、17歳前後の発作が多く、家族のなかに広場恐怖症で困っている人がいる場合に発症しやすい
といわれています。
たとえば、、、
- 広場恐怖の対象となりやすい状況の例
- 交通機関に乗る(電車、新幹線、飛行機、高速道路)
- 閉鎖空間にいる(映画館、劇場、エレベーター、トンネル)
- 解放空間にいる(大駐車場、市場、橋)
- 行列に並ぶ、人ごみの中にいる
- 1人で外出する、1人で留守番をする
【非発作性不定愁訴】
慢性期になると、パニック発作よりも穏やかな症状が持続的に出現することも。
- ■非発作性不定愁訴の例
- 身体がゾクゾクして鳥肌が立つ
- 頭痛
- 動悸がする
- 視界がチカチカする
- 息苦しくなる
- 首の痛み
- じっとりと汗をかく
- 頭に何か乗っているような感じ
- 喉元がピクピクする
- 手が冷たい
- 汗がひかない
- いつも雲の上を歩いているような感じ
- 肩こり
- 背中がピクンピクンする
- 胸が痛くなる
※医療法人和楽会:パニック症より
女性は男性の3倍パニック障害が多い
平成12年11月に全国47都道府県の20代から60代の男女それぞれ400人に対して合計4,000人の健康調査が行われました。筆者はパニック障害に関する部分を担当しました。
その結果、パニック障害の患者であると考えられる人は135人いました。
これは100人の人がいるとその中の3.4人が現在または過去にパニック障害に罹患している/したという計算になります。
パニック障害の経験がある人の割合を男女別で見ますと、
女性は100人に5.1人、
男性は100人に1.7人で、
女性は男性の3倍パニック障害が多いということになります。
年代別に見ますと
女性では30代(6.2%)、20代(5.7%)、60代(5.1%)の順で、
男性では30代(2.3%)、40代(2.2%)、20代(1.8%)の順でした。
広場恐怖を示す人はパニック障害よりはるかに多く、100人に22.1人でした。
5人に一人は広場恐怖があるという計算になります。
男女別で見ると女性は100人に25.4人で、男性の100人に18.7人より多い結果が出ました。
広場恐怖の対象に関しては、トンネル、エレベーター、橋などの狭いところを恐れる人が8.0%でもっとも多く、すぐにトイレに行けない状況を恐れる人が6.8%、自動車の運転、特に高速道路や渋滞を恐れる人は5.3%、電車、バス、地下鉄、航空機などの公共交通機関を恐れる人が4.9%、美容院、理髪店、歯医者、会議、行列に並ぶといった精神的な束縛状況を恐れる人は4.4%でした。
広場恐怖の人の数はパニック障害の人の6倍以上という計算になります。
病気になった人を初めてみる医者の立場からすると、広場恐怖はパニック発作が生じてその結果起こるものだと解釈しやすいですが、このような客観的なデーターからすると、どうもそうではなく、もともと広場恐怖の傾向があり、その上にパニック障害が発症することもあると考えた方が適切かもしれません。
さて、この調査でもう一つ大変興味深いことがわかりました。高度な統計的手法を使って、パニック障害の発症に関連のある項目を検討したのです。
その結果、女性では「運動をしないこと」と「ストレスに対処が下手なこと」でした。
一方、男性では、「年間温度差の激しい地域」でのパニック障害の頻度が高いことがわかりました。
筆者が以前クリニックの患者さん500人以上について調べた調査では、気温が上昇する時期(5,6,7月)にパニック発作の発症が一番多いことがわかっていますから、パニック障害の発症は温度が関係する可能性があるのでしょう。
→ パニック障害入門:パニック障害は増加しているのか

なぜパニック障害になるのか
発達障害の人が、パニック障害を引き起こす比率はとても高いといわれています。発達障害のない人に比べて倍以上だとか。
また、、、
うつ病とパニック障害を併存している例も非常に多く
これは、、、
パニック障害が、うつ病になる前段階として現れている
こういった場合は、パニック障害の治療中に、少しずつうつ病に症状になっていくことがあるようです。
ですが、、、
なぜパニック障害になったのかという原因に関しては、まだ十分に解明されていません
考えられている仮説は、以下の3つです。
- 脳機能の異常
- 心理的要因
- 社会的要因
1度パニック障害を起こすと、そのパニック発作が起きたものや環境になると再び発作が起きやすくなります。
たとえば、、、
- 朝の通勤電車で、降りる駅が近づいたら、動悸と息切れがたまたま起きた、苦しかった
- 次の日の朝、また降りる駅が近づくとあの動悸と息切れが起きるのではないかという不安
朝、通勤電車、降りる駅といったキーワードがパニック障害を大きくしていく、本来ならば関係の無い3つの要素が、結びあいパターン化されることで重症化していきます。
パニック障害の治療とは
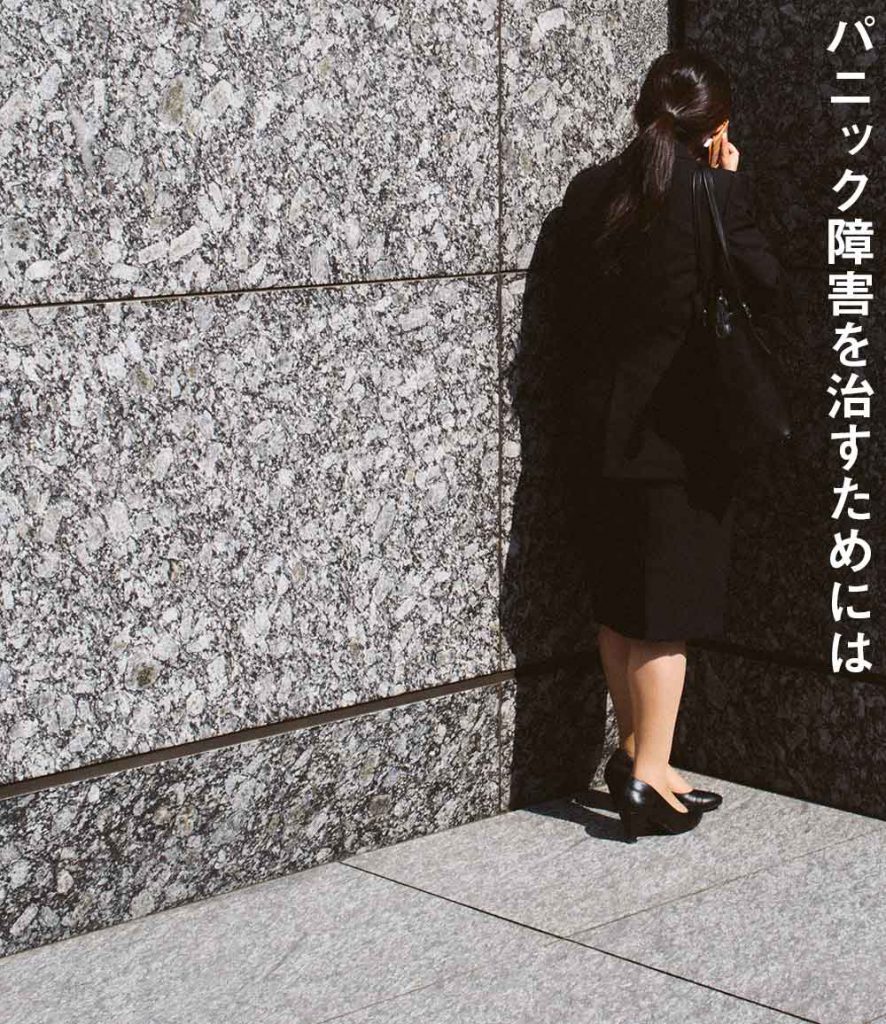
パニック障害を治すためには
パニック障害で、自殺未遂や衝動行動などの問題的な行動を起こすことはまれだといいます。また、比較的治療しやすい病気です。
パニック障害で、、、
- そのまま、治療をしなくても自然に完治する人
- 通院して、薬物療法で完治する人
苦手な状況を克服していく
本来ならば関係の無い3つの要素(朝、通勤電車、降りる駅)を1つずつ克服する方法が大切です。
最初から、環境的な要因や物質的な要因を全部合わせて克服するのは無理があります。
たとえば、、、
- 電車なら=昼の時間帯に電車に乗ってみる(一駅でも)
- 降りる駅なら=乗る電車のルートを変えてみる
- 朝なら=乗る駅を自転車などで1つ先の駅に変えてみる
などの工夫をしてみるのよいと思われます。
うつ病や発達障害ではなく、パニック障害のみの症状ならば、、、
パニック障害は、よく知られている病気なので、会社や上司、産業医に相談することも解決方法の1つです。
たとえば、会社や上司、産業医に相談して、、、
- 通勤の時間帯を変えてみる
- 通勤ルートを変更する
などの工夫で、改善が図れます。
ただし、これも主治医との話し合いから進めることが大切です。
以上。
- 参考文献
- 厚生労働省:パニック障害・不安障害
- 公益社団法人 日本精神神経学会:塩入俊樹先生に「パニック障害/パニック症」を訊く
- パニック障害入門
- 東洋経済:「パニック障害」10人に1人がかかる病の対処法
- 病気スコープ:パニック障害
- 医療法人和楽会:パニック症
また、次回。
Thank you very much for providing photos and illustrations.
- pakutaso
- irasutoya
- Photo by Tore F on Unsplash
- Photo by Manuel Velasquez on Unsplash
- Photo by Charles Deluvio on Unsplash