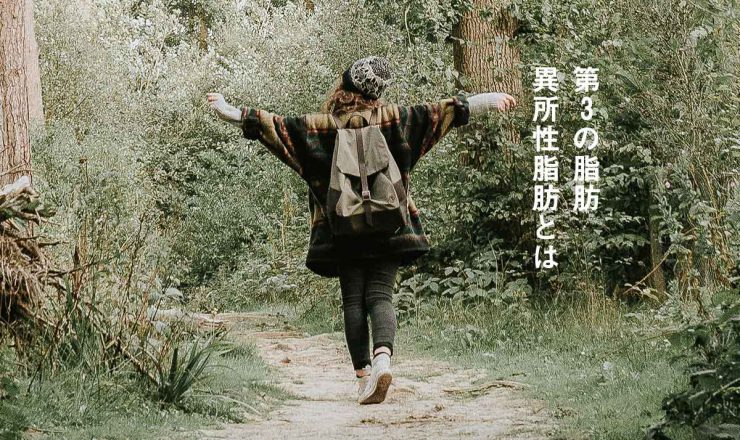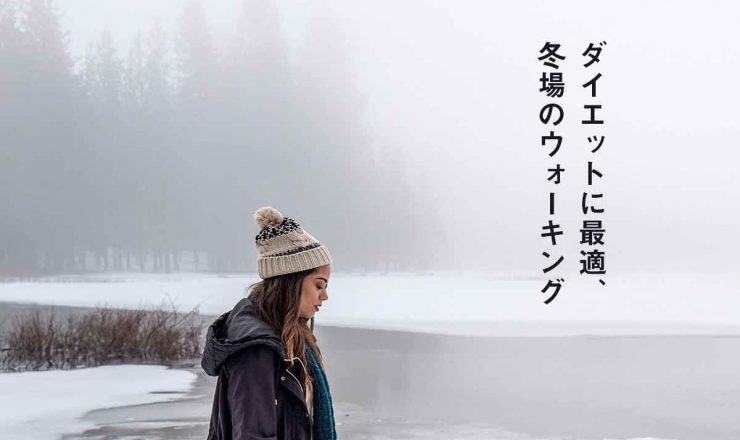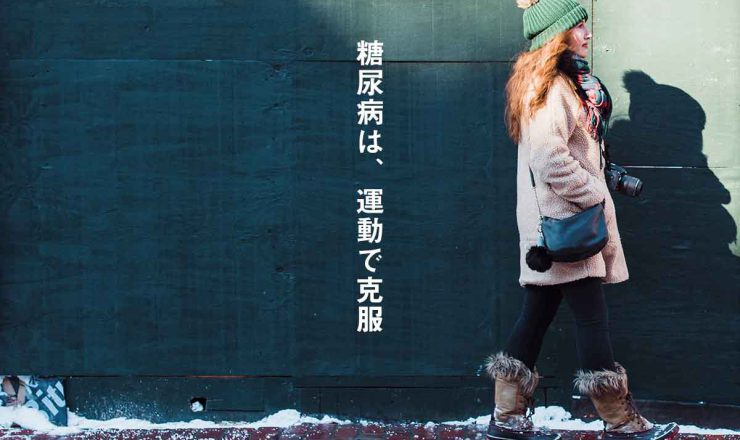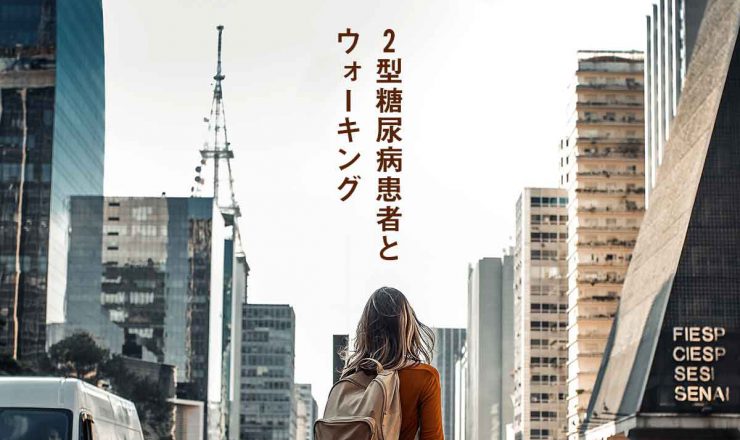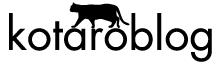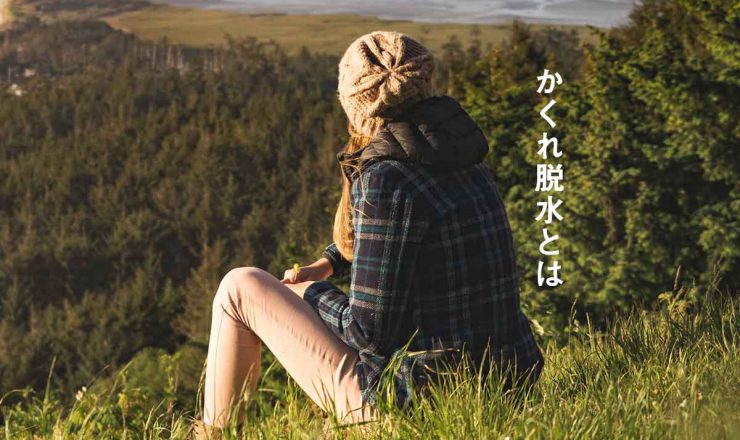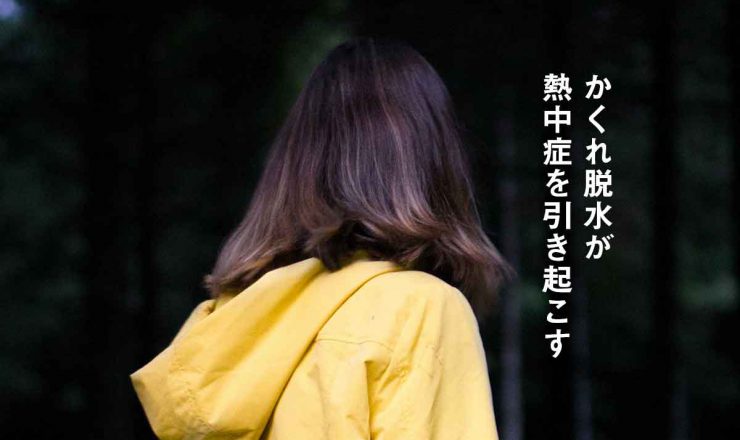連日の猛暑で、身体は疲労困憊、汗はダラダラ、いい加減にして欲しい。脱水症で倒れそう。
と、いうかたへ。

脱水状態になっているのかどうかって、ほんとうにわかりづらい。
気分が悪くなってようやく、かくれ脱水だったことが判明したとかよくあります。
かくれ脱水は危険なので要注意です。
今回は、かくれ脱水の見分け方の話です。
■もくじ
- かくれ脱水を見分ける方法
- かくれ脱水にならない予防法
この記事を書いている僕(コータロー)は、健康食品を販売して15年ほど。
かくれ脱水を見分ける方法
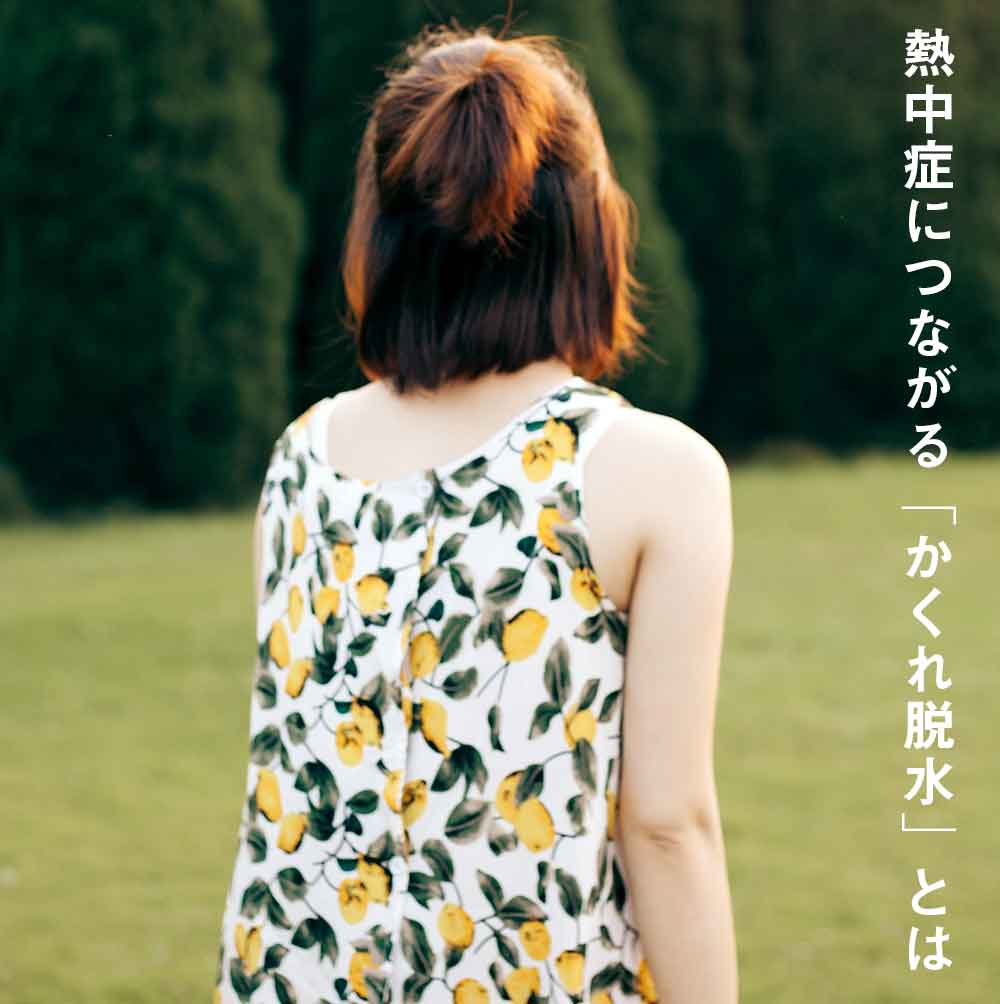
熱中症につながる「かくれ脱水」とは
真夏になると連日のようにニュースで「熱中症」で救急搬送された人数の多さを知らされます。
たとえば、、、
熱中症、全国で1週間に1万2千人搬送 都内79人死亡
2020年8月18日では、
総務省消防庁は18日、10~16日の1週間に全国で熱中症で救急搬送された人は、前週からほぼ倍増となる1万2804人だったと発表した。そのうち死者は30人。気象庁によると、10日は猛暑日となった観測点が今年初めて100地点を超えた日だった。
東京23区では18日、前日までに死亡した26人の死因が熱中症だったと新たに確認され、80代女性が亡くなったとみられる2日以降、熱中症による死者は79人となった。都監察医務院によると、60歳以上が屋内で見つかるケースが大半で、その多くは部屋にエアコンがないか、あっても発見時に作動していなかったという。
東京消防庁によると、熱中症とみられる症状で救急搬送された人は18日午後9時現在、稲城市と島嶼(とうしょ)部を除く都内で1~96歳の男女193人に上った。60代と80代の男性2人が重篤、40~90代以上の男女7人が重症で、中等症78人、軽症106人だった。
→ 朝日新聞デジタル
猛暑というか酷暑になると、「熱中症」という言葉が氾濫します。そして、その数はうなぎ登りに増えていきます。
- 2020年8月3日~8月9日のデータでは、熱中症によって救急搬送された数は、6664人。
- 翌週の8月10日~8月16日では、なんと倍の1万2804人
熱中症搬送者数 前の週の約2倍に
総務省消防庁が18日発表した熱中症による救急搬送者数のまとめによると、先週(8月10日~16日)熱中症で救急搬送された人は全国で12804人(速報値)でした。その前の週の6664人(速報値)の約2倍で、週ごとに多くなっています。先週は最高気温が40度を超えた所があり、14日からは、最高気温が35度以上の猛暑日となったアメダス観測地点が200地点を超える日が続いています。
熱中症が発生した場所で最も多かったのは「住居」の48.3%で、家の中でも熱中症になってしまうということを表しています。家の中でも無理をせず、適切に冷房を利用するなどして予防を心がけてください。また、搬送者数の内訳をみると、61.8%が65歳以上の高齢者が占めています。高齢者や小さい子どもに対しては周りの人が声を掛けるようにして、熱中症にならないよう注意してください。
→ 天気.jp

熱中症は、高温の環境の下で作業をしたり、風通しのない室内で過ごしていたりすると、脱水症状になり、水分が体内に少ないことで、臓器が十分機能しなくなり、意識障害やこむら返りなどの症状などの障害でる総称をいいます。
また、、、
大量の汗によって、体液(水分と電解質)が失われます。
すると、さまざまな症状が身体に表れてきます。
- 脳:めまい、立ちくらみ、集中力・記憶力の低下、頭痛、意識消失、けいれん
- 消化器:食欲低下、悪心(おしん)、嘔吐、下痢、便秘
- 筋肉:筋肉痛、しびれ、まひ、こむら返り
かくれ脱水に関する情報は、この記事でも詳しく解説しています。
熱中症につながる「かくれ脱水」のサインとは
人の身体には、たくさんの水分量が含まれています。
- 成人男性が体重のおよそ60%
- 成人女性が体重のおよそ55%
- 高齢者なら50%
- 赤ちゃんは、70%。
そして、、、
血液の量は、その人の13分の1といわれています。たとえば、65キロの人ならば、約5キロが血液の量になります。
どれだけの量が失われると『脱水』なのか
脱水症の症状は、その人の体重の減少によって判断されます。
たとえば、、、
- 1~2%の体重の減少では、軽度の脱水症
- 3~9%の体重の減少では、中等度の脱水症
- 10%以上になると高度の脱水症
- それ以上になると生命の危険が生じます
そして、困ったことにこの『脱水症状』は、自覚できない場合が多いです。このことを【かくれ脱水】といいます。
この、、、
【かくれ脱水】は、熱中症を増やす大きな原因になっています。
[かくれ脱水]で特に注意が必要なのは高齢者と子ども
多くの健常な大人でさえ熱中症になるのですから、[高齢者と子ども]は注意が必要です。
[かくれ脱水]の高齢者
高齢者は、「口渇中枢」といわれる喉の渇きを感じる感覚が鈍くなっています。水分が必要な状態でも「喉の渇き」が分かりづらくなっています。さらに、身体にためる水分を保持する筋肉が少ないことも影響しています。
また、高齢者の方で多くあるのは、夜中にトイレに起きるのを嫌がって水分を摂らないようにしている人も多いです。さらに、エアコンをつけたがらない傾向もあります。周囲に気遣いが大切です。

[かくれ脱水]の子ども
子どもの場合は、「のどが渇いているから何かを飲ませて」ともいえず、また表現できない場合がありますので、まわりの大人の気付きが必要です。さらに、汗をかく機能や腎臓の機能がまだ未発達であることも関係しています。
そして、子どもはその成長する過程で、多くの水分を必要としていますから、常に水分の補給が大切です。
また、、、
子どもの場合は、皮膚や呼吸から失われる水分が、大人に比べ約1.7倍もあります

[かくれ脱水]になっているかなっていないか。
脱水症状になっていれば、以下のようなポイントで判断できます。
- 食事量が減っている
- 37度以上の発熱が24時間以上続いている
- いつもより汗が多い
- 尿の回数が少なく、量も少ない
- 便秘気味
- いつもより意識がハッキリしない
[かくれ脱水]かどうかのチェック方法
![[かくれ脱水]かどうかのチェック方法](https://kotaroblog.jp/kotaroblog/wp-content/uploads/2020/08/du-wei-EkQ0tpZ_xXQ-unsplash274-1024x774.jpg)
[かくれ脱水]チェック方法:その1
握手をしてみる
握手をしてみて、手が冷たければ[かくれ脱水]の可能性が大きいです。
理由として、脱水状態になっていると、血液は、臓器に集中しますので、手足が冷たくなります。

[かくれ脱水]チェック方法:その2
ベロを見せてもらう
ベロを見せてもらい、渇いていたら[かくれ脱水]の可能性があります。
理由として、脱水状態になっていると、唾液が減少しています。ですから、舌の表面も乾燥します。

[かくれ脱水]チェック方法:その3
皮膚を摘まんでみる
皮膚を摘まんで、つままれた形が、3秒以上も戻らなければ、[かくれ脱水]になっています。
理由として、脱水状態になっていると、皮膚に弾力性がなくなっています。
[かくれ脱水]チェック方法:その4
親指の爪の先を押してみる
親指の爪の先を押してみて、赤身が戻るのが遅ければ[かくれ脱水]の可能性が大きいです。
理由として、脱水状態になっていると、血液が手足に行き渡っていないので[かくれ脱水]の徴候が出ています。
[かくれ脱水]チェック方法:その5
高齢者の脇の下を確認する
高齢者の脇の下が、渇いていたら[かくれ脱水]の可能性が大きいといえます。
理由として、通常の高齢者なら脇の下は汗にひる潤いがあります。
かくれ脱水にならない予防法

[かくれ脱水]にならないためには、規則正しい生活を
人の身体は、1日に約2.5リットルの水分を必要としています。1リットルは、食べものから生成され、300ミリリットルは、代謝から補充されます。残りの1.2リットルは、飲みもので補わなければなりません。
ですから、水分補給は脱水症を起こさないためにも大切なことです。
一気に1.2リットルもの水分と摂るのは、ムダですから、こまめに摂るようにしてください。

大切なことは、、、
のどが渇く前に、水分を補給することです。1日6~8回ぐらいに分けて飲むようにしましょう。注意する点は、アルコールは利尿作用があるので水分には入れてはいけません。

[かくれ脱水]にならないために十分な睡眠を
体温を調節しているのは、[自律神経]です。規則正しい生活を送ることで、[自律神経]は正常に働きます。交感神経と副交感神経を上手く機能させるには、睡眠の質を向上させることが大切です。

[かくれ脱水]にならないためには暑さに慣れる
夏の暑さに慣れることが大切です。というのは、暑さに慣れていないので発汗が上手にできていません。
暑さに慣れる手っ取り早い方法は、有酸素運動です。運動することで、発汗作用が高まります。また、血液の循環もよくなるので、万病の元である低体温を解消することができます。
さらに、血流がよくなれば新鮮な酸素や栄養を速やかに全身に行き巡らせることができ、老廃物を取り除くことができます。

以上。
- 参考文献
- 厚生労働省:「健康のため水を飲もう」推進運動
- 済生会:“コロナ夏”の「かくれ脱水」・熱中症対策
- 日本成人病予防協会:かくれ脱水
- 「かくれ脱水」を予防しよう。
- e健康ショップ:健康レッスン1・2・3!
あなたを守る「ミネラル濃縮液」ミネラルくん
また、次回。